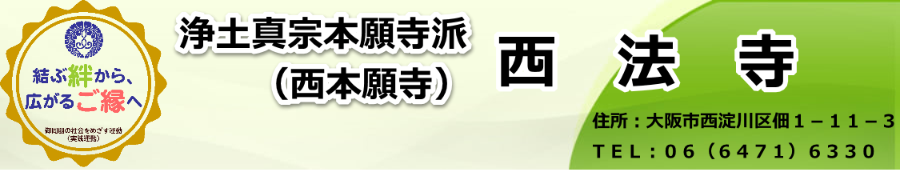2024年5月
他人に対しては、すぐ裁判官になるが
自分に対しては、すぐ弁護士になる
今月の言葉、様々な場面で、思い当たります。
たとえば、、、
子どもが、お手伝いでお皿洗いをしてくれていた時、音がします。
ガチャーーン!
「あ、お皿割ったな」、と思います。
でも、自分がお皿を洗っていて、ガチャーン!となると、
「あ、お皿が割れた」、となりませんか。
他人が割ったときには、その人が割ったのです。
でも、自分が割ったときは、私が割ったのではない、お皿が勝手に割れたのです。
意識していなくても、そんな言葉遣いをしてしまう。
どうでしょう。思い当たりませんか。
人の失敗に対しては、テレビにまで文句を言い、
自分の失敗に対しては、情状酌量を求める。
無意識で、他人を責め、自分を守ってしまう。
だれもがそんな心を持っていると思います。
知らず知らずのうちに、ある時は裁判官の仮面を着け、またある時は弁護士の仮面を着ける。
さまざまな仮面を、とっかえひっかえ、付け替えながら過ごす自分に気づかされます。
でも、どのような仮面をかぶっていても、阿弥陀さまは、その仮面の下にある、「本当の私」をご存知です。
弱く、孤独な存在だとご覧になられ、お慈悲の心で温めてくださいます。
北風と太陽。
あたたかさの中で、仮面を外し、何者でもない「本当の私」に戻ることができる。
それも、仏さまの前に座る時間なのかもしれません。
称名相続
2024年4月
うぐいすの一声は、春のすがた。
お念仏の一声は、阿弥陀さまのすがた。
春らしい、あたたかな日が増えました。
春の訪れを告げるものとして「梅とウグイス」の取り合わせが言われます。
ウグイスは、「春告鳥(はるつげどり)」とも呼ばれ、日本人は昔から「ホーホケキョ」という一声に春の訪れを感じてきました。
気象庁や環境省では、今でも、ウグイスの初鳴きによる春の訪れを、観測し、データで残しているそうです。
ウグイスの「ホーホケキョ」は、昔から現代にいたるまで、日本に春の訪れを告げる、一つの確かな指標といえそうです。
春は、目には見えません。
でも、梅が花をつけ、ウグイスが鳴くところに、春のはたらきを知らされます。
阿弥陀さまも、目には見えません。
でも、南無阿弥陀仏のお念仏がこぼれるところに、阿弥陀さまのはたらきを知らされます。
原口針水という和上さまが、こんな歌をのこされています。
声に姿はなけれども、声のまんまが仏なり。
仏は声のお六字(南無阿弥陀仏)と、姿を変えて我に来る。
梅とウグイスに、春の温かさを感じるように、
お念仏するなかに、阿弥陀さまに抱かれた温もりをいただきます。
称名相続
2024年3月
毎日、「これが人生最後の日だ」と思って生きなさい。
やがて必ず、その通りになる日が来るから。
ちょっとドキッとするこの言葉。
アップルの創業者、スティーブ・ジョブズの言葉だそうです。
彼は、毎日鏡に向かって、今日やることは本当に自分のやりたいことなのか、と問いかけて、
ノーが続くと、そろそろ人生の目標や自分のあり方を変える時だと考えていたそうです。
脳科学者の茂木健一郎さんが、「脳は、コントラストで学ぶ」とおっしゃっていました。
白は、白だけでは、分かりにくい。
が、隣に黒を置くと、白の白さが分かる。
なるほど、本当だなと思います。
生きるということも、同じかもしれません。
生きるということは、生だけでは、分かりにくい。
が、隣に死を置くと、生きるということがより鮮明になる。
そして、安心してください。
死は、絶望ではありません。
阿弥陀さまは、死は、不幸なことでも、でもかわいそうなことでもなく、お浄土参りの日、仏さまのいのちをいただく日だとおっしゃいます。
懐かしいお方々とまた会える日なんだと教えてくださいます。
だから、お念仏いただく者にとっては、死を隣に置くというのではなく、お浄土参りを隣に置くといいのかもしれません。
そうすれば、生が、冷たい緊張感で支えられるのではなく、じんわり温められているような気がします。
今日を、尖った時間としてではなく、支えられている時間として過ごせるような気がします。
大切なあの人とお浄土で再開した時に、胸を張って会えるように、楽しく笑い合えるように、今日という日を丁寧に歩んでいければと思います。
称名相続
南無阿弥陀仏
2024年2月
悲しみは、悲しみを知る悲しみに救われる。
涙は、涙にそそがれる涙に助けられる。
今年は、北陸の地震から始まり、一か月たった今でも、復興の遅れが報道されています。
私たちの知る内容のその裏には、もっともっと多くのお方々の悲しみがあることは、想像に難くありません。
関西にいるからでしょうか。
阪神大震災の経験者のお方々が、北陸の被災地に入り、救援活動をなさっているニュースが多く流れます。
その姿を知るたびに、今回の言葉が思い起こされます。
この言葉は、金子大栄というお東の僧侶の言葉です。
当然、南無阿弥陀仏でご一緒くださる、阿弥陀さまのことが想定されています。
ですが、娑婆に生きる我々が、お互いに身を寄せ合い、力を合わせながら生きていく姿にも、重ねて味わわれます。
深川倫雄という和上さまが、敬老の日に寄せて、こんな言葉をのこされています。
・毎年、九月になると、新聞をはじめとして、世間さまざまに、老人を思い出す。
・敬老の行事があり、年寄にやさしい言葉が、はやる。
・10月から、あくる8月までは、忘れられている。
・それでも、9月に思い出してもらえるのは、敬老の日を決めてある政治のおかげであろうか。
・老いてゆくということは、余の片隅に押しやられてゆくということであろうか。
・老人は、寂しいのである。
・片すみに押しのけられるということは、寂しいことである。
・それでも、おぼえていてくれるということは、うれしい。
・忘れられてしまうということほど、おそろしく、つらいことはない。
・つまらぬものでございます、とは申せ、あなたは誰でしたかね、といわれるほど、悲しいことはない。
・覚えているということは、最後の愛情である。
・単に覚えているだけでなく、真ん中において、ちやほやしてもらいたい。
・ところが、ちやほやする人より、じっと覚えている人の方が、愛情は、深く大きいのではないか。
・覚えているということは、最も深い愛情であろう。
・覚えているぞ、という喚び声が嬉しい。
悲しみの報道を見るたびに、覚えておくということの大切さを、思います。
称名相続
南無阿弥陀仏
2024年1月
謹賀新年 あけましておめでとうございます。
昨年は、この掲示伝道、ウェブサイトの解説にお付き合いくださいまして、有難うございました。
新しい年も、皆さまが、仏さまの言葉とともに歩まれますよう念じております。
本年も、何卒、よろしくお願い申し上げます。
称名相続
南無阿弥陀仏
2023年12月
渋柿の、渋こそよけれ、そのままに、変わらで変わる、味のうまさよ
お参り先のご門徒さんから、渋柿をいただきました。
「見た目は悪いけれど、味は抜群ですから。」
そのお言葉の通り、とてもおいしい渋柿でした。
以前、お寺には、渋柿の木がありました。
幼いころ、よく木登りして、落ちたりした覚えがあります。
その渋柿の実がなったとき、親に確認して、一度、かじってみたことがありました。
衝撃的な渋さ。
喩えるなら、口の中全てに、オブラートがビチッと張り付いて、うがいをしようが牛乳を飲もうが一切取れない、気持ち悪い感覚でした。
二度と、二度と、かじるまいと誓いました。
その渋柿が、なんと、皮をむいて、お日様に干すだけで、渋みがそのまま甘味に変わる。
初めて知ったときには、これまた衝撃でした。
阿弥陀さまのお救いをあらわすとき、この渋柿に喩えられることがあります。
私は、渋柿。
阿弥陀さまが、お日様です。
私が身に具える煩悩が、阿弥陀さまのはたらきによってそのまま功徳となります。
見た目は変わらないけれど、照らされ温められることで、南無阿弥陀仏がこぼれるほどの身となります。
親鸞聖人は、このことを御和讃でよろこばれます。
無礙光の利益より 威徳広大の信をえて
かならず煩悩のこほりとけ すなはち菩提のみづとなる
罪障功徳の体となる こほりとみづのごとくにて
こほりおほきにみづおほし さはりおほきに徳おほし
この身の上には、煩悩が一杯です。
でもだからこそ、阿弥陀さまの功徳も一杯です。
罪を抱えるまま、尊い命を歩ませていただきます。
称名相続
南無阿弥陀仏
2023年11月
午前の法則を、人生の午後に持ち込む人は、心に大きな苦を受ける。
今月の言葉には、もとネタがありまして。
哲学者のユングと言うお方が、こんなことをおっしゃったそうです。。
「午前の法則を、人生の午後に引きずり込む人は、心の損害という代価を支払わなければならない。」
「午前」や「午後」と言っているのは、きっと人生についての事でしょう。
つまり、若いころに獲得した人生の法則は、老年になると通用しない、ということでしょう。
どういうことかと考えてみれば、人生の後半には、その価値観が変わっていくということが言えそうです。
歳を重ねると、色々なことに気づかされます。
若いころは、恥をかくのは嫌で、遊ぶことしか考えず、勉強は嫌なものです。
ですが、歳を重ねると、もっと恥をかいておけばよかった、もっと様々なことに挑戦しておけばよかった、もっと勉強しておけばよかった、そんな風に感じませんか。
おいしいと感じるものも、変わります。
脂っこい唐揚げや焼肉が大好きだったのが、お野菜中心の和食に落ち着きます。
そして、「当たり前」の内容も変わっていくのではないでしょうか。
健康で、当たり前。動けて、当たり前。家族や友達がいて、当たり前。
生きていて、当たり前。命があって、当たり前。明日があって、当たり前。
ところが、人生の午後には、この「当たり前」が、「当たり前」でなくなります。
これまで当たり前だったことが、当たり前でなくなる時に、人生の午後になるのかもしれません。
人生の夕暮れにさしかかった時、人はさみしさを覚えるようです。
そんなときにこそ、あたたかく響くのが、南無阿弥陀仏のお念仏です。
お念仏の中に、阿弥陀さまがおっしゃいます。
「ひとりじゃないよ、ひとりじゃない。私がいつも、ほら、一緒だよ。」
そのことを味わうために、またお念仏をいただきます。
歳を重ねれば重ねるほど、あたたかくなるのが、お念仏の味わいではないでしょうか。
そんなことを思った、今月の言葉でありました。
南無阿弥陀仏
2023年10月
夕焼けて 西の十万億土 透(す)く
インターネットを見ていて、出会った俳句です。
お寺の月参りでお勤めする『仏説 阿弥陀経』。
そこには、「ここより西方、十万億の仏土を過ぎて、世界あり。名付けて極楽という。」と示されます。
私の感想ですが、この俳句では、お浄土のことが詠われているのではないでしょうか。
夕焼けがあまりにも美しく、お浄土が目に浮かぶようだ。
そんな感動を詠われたのだと、勝手に解釈しています。
うちの娘が幼稚園の時、神戸フルーツフラワーパークに遊びに行きました。
小高い丘の上から、娘をおんぶしながら、町に沈みゆく夕陽を見ました。
すごく美しい景色でした。
背中の娘に言いました。
あの夕日の向こうに、仏様の国があるそうよ。
命が終わったら、優しい仏さまに抱っこされて、みんなそこに生まれていくそうよ。
すると、背中の娘が言いました。
へ〜。きれいだね〜。行ってみたいな〜。
どのようなものにも感動を与え、
どのようなものでも、行ってみたいと思わせる。
お浄土には、そう思わせるご用意がある。
そんなお浄土の土徳を、教えられた出来事でした。
9月は、お彼岸の季節です。
真西に沈む太陽をご縁に、命の帰り往くお浄土を思う季節です。
南無阿弥陀仏
2023年9月
人間関係は、鏡である。鏡は先に、笑わない。
今月の言葉は、人間関係をあらわす言葉です。
人間関係は、鏡である。鏡は先に、笑わない。
なるほどな、と思わされます。
笑顔を求めたときに、鏡の方が先に笑いかけてくることはありません。
自分が笑顔を向けたとき、はじめて鏡の中の自分も笑いかけてきます。
人間関係も然り。
他人に笑顔を求める時は、こちらの笑顔が先だよと、教えてくれる言葉です。
大切なことだな、と思います。
ひるがえって、仏さまのことを思います。
善導大師の言葉には、次のようなものがあります。
「読誦大乗」と言ふは、これ経教はこれを喩ふるに鏡の如し。
しばしば読み、しばしば尋ぬれば智慧を開発す。
意味は、二通りあるようです。
一つは、現代の鏡としての理解。
経教に説かれる人間のありようを自分の姿鏡として尋ね、自らを修正すべし。
一つは、古代の鏡としての理解。
何度も磨かなければくすんでしまうように、経教を何度も尋ね磨いて、初めて智慧が開かれる。
私は、後者の方が好きです。
なぜなら、仏法は、姿見の鏡のように、後から動くものではないからです。
阿弥陀さまは、こちらが動く前から、先に動いてくださる仏さまです。
私が願う前から、頼む前から、先に立ち上がり、先に来てくださる。
だから、今、この口に、お念仏の声となって、ご一緒です。
人間関係は、鏡である。鏡は先に、笑わない。
仏法は、鏡ではない。鏡は先に動かない。
そんなことを思った、今月の言葉でありました。
南無阿弥陀仏
2023年8月
亡き人の 願いに出遇い 手を合わす
8月は、お盆の季節です。
お盆は、日本最大の仏教行事だそうです。
最近のテレビでは、「レジャーの季節」として報道されているような気もしますが、
ぜひ、お墓参りをしていただきたいと思います。
お墓参りをすることは、ご先祖様を思う、自分の命の根っこを訪ねることです。
また、亡きお方のことを思うことで、そのお方と出会い直していくことでもあります。
お墓の前に立つ時間を、人は、どのように過ごすでしょうか。
そのことを味わう、さまざまな言葉があります。
・「そやったん」 言うてほしくて 墓参り
・親の背を 流すごとくに 墓参り
・亡き人を偲んでいると 独り言が 独り言でなくなる。
・亡き人と、声なき声、言葉なき言葉で、会話する。
さまざまな味わいがあり、どれも有難く思います。
亡きお方々は、今、仏さまとなって、何を願っておられるのでしょうか。
それは、後の世を生きる私たちの、幸せです。
今、墓前に足を運び、手を合わせ、お念仏し、頭を下げています。
お墓参りの準備をし、実際に来た、そのことが、今、亡きお方の願いに包まれているすがた、そのものです。
亡きお方は、遠くにおられるのではありません。
短い期間だけ、帰ってこられるのではありません。
いつでも、どこでも、南無阿弥陀仏のお念仏となって、ご一緒くださいます。
「独りじゃないよ、一緒だよ。」
そのことを、南無阿弥陀仏の声で、知らせてくださいます。
そのはたらきにつつまれて、促されて、今墓前に立ち、お念仏している。
そのはたらきに支えられたいのちであると、命の根っこを確認する。
それが、お墓参りの一つの味わいではないでしょうか。
称名相続